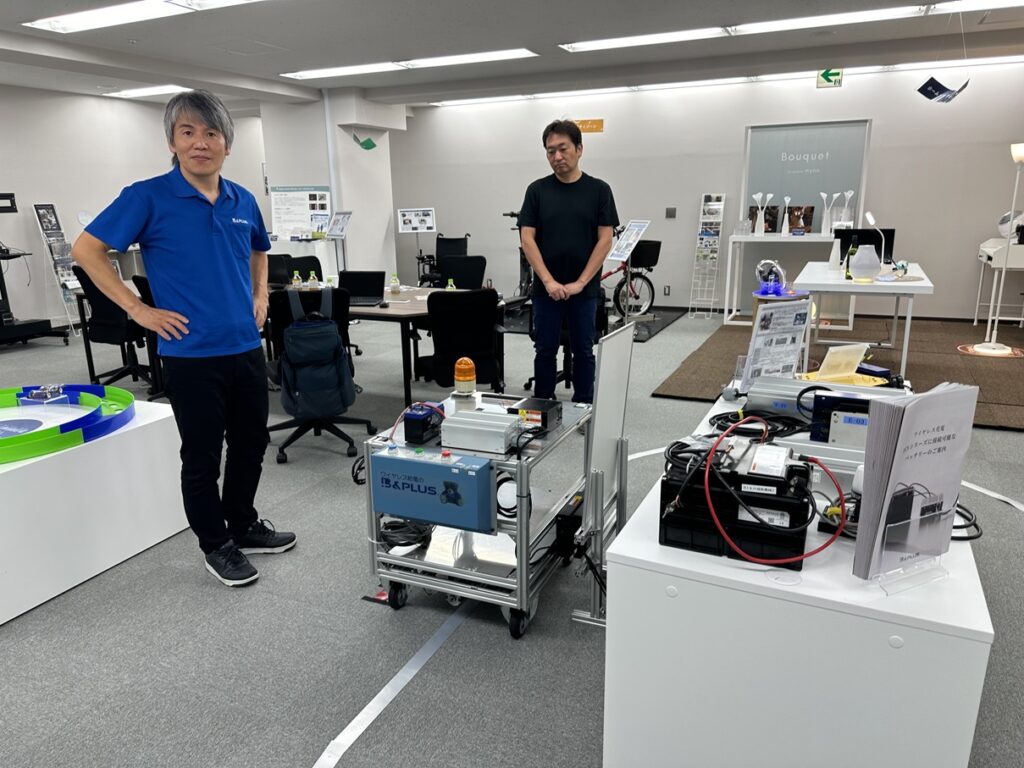2024.09.13
2024年9月13日(金)
手段より目的観、実態把握、ポジティブ営業
1000 セコム来社
調印
1400 日本IT打合せ
カイゼン進捗
1400 カトー社来社
契約書
1530 日経社来社
1630 宮崎先生ZOOM
小学生の探究をどのように行うか。
1930 会合
それにしても、中津の海沿いで見たコレ。何だったのだろう。
●今日の学び
立命館大学 山本 圭 准教授
自分の損得には影響ないはずなのに、他人が利益を得ることを受け入れられない。
そんな下方嫉妬が、社会を生きづらくしている一因であるように思います。
(中略)
民主主義では平等が中心的な価値になります。しかし、どんな社会であっても
完全な平等というのはあり得ず、少なからず差異は生じます。
そして嫉妬が比較を条件とするとすれば、相手との差が縮まれば縮まるほど、
その差がより気になって比較が生じ、嫉妬感情が膨らんでいくのです。
そう考えると、嫉妬は民主的な社会で不可避な感情であり、
どうにかなくそうとするよりも、どう付き合うかを考えることが
より現実的な選択肢と言えます。