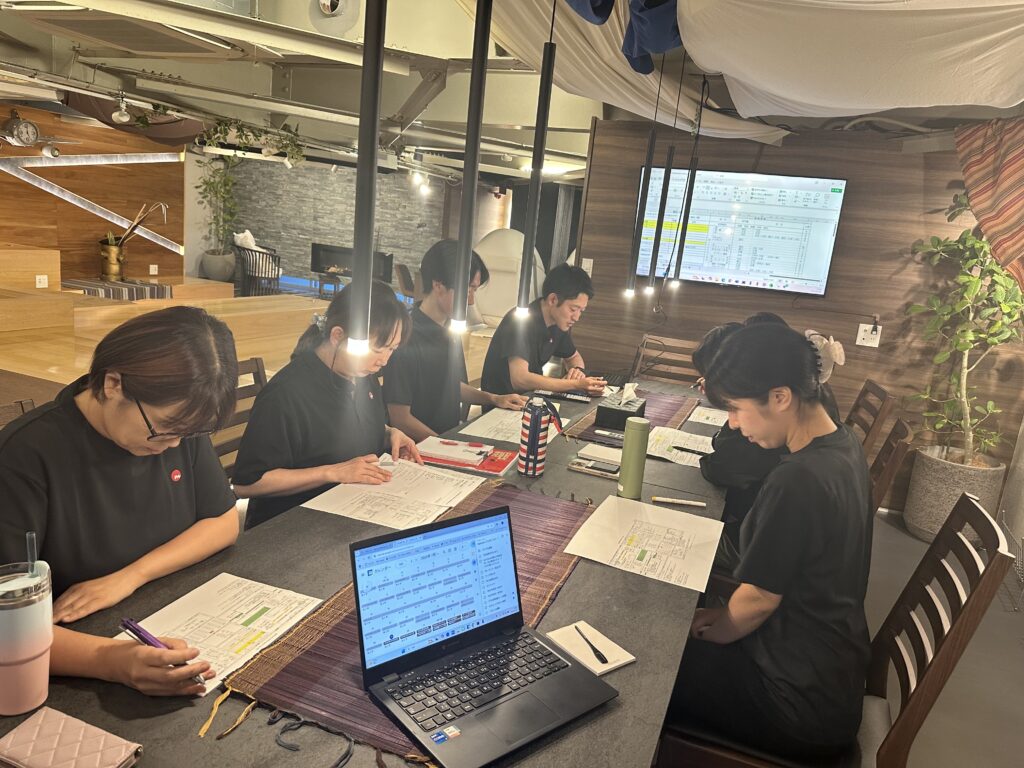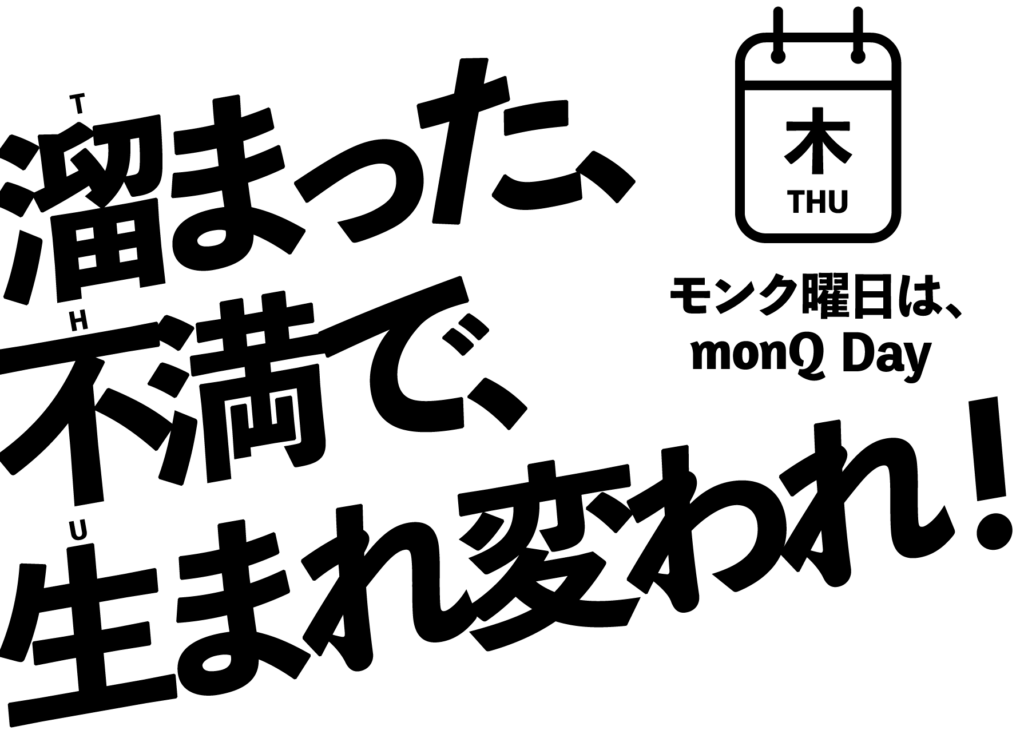2025.07.30
2025年7月30日(水)
二重被ばくした祖父を持つ原田小鈴さん。
広島のエノラ・ゲイと、長崎のボックスカーの両方に乗った祖父を持つアリ・ビーザーさん
とのドキュメンタリーを紹介。涙で言葉に詰まった朝礼になった。
原爆を「落とした」祖父と「落とされた」祖父
https://www.youtube.com/watch?v=Pwqrx3FarkQ
それが当たり前(いつでも政治・宗教・戦争・平和の事を語り合える)
の世の中になると良いと思う。
0930 ジェトロ打合せ
1100 小野塚氏来社 新たな最終戦略。
1400 UNHCR三堀氏打合せ
1500 MIYOSHIDAカップ打合せ
1930 水曜勉強会「能力主義と傲慢の克服」
警察からの捜査協力依頼に対応。
●今日の学び
事故を防ぐ要諦とは何か―それは、
しっかりと基本を守るということ。
その積み重ねのなかに人生の輝きがある。
●きょう30日は、国連が制定した「国際フレンドシップ・デー」。
国を超えた友情が世界平和を築くことを再認識する日だ。
人類の幸福を目指す広宣流布の運動には、国境も民族の壁もない。
世界の同志と心を合わせ、対話の力で共生の未来を開いていきたい。