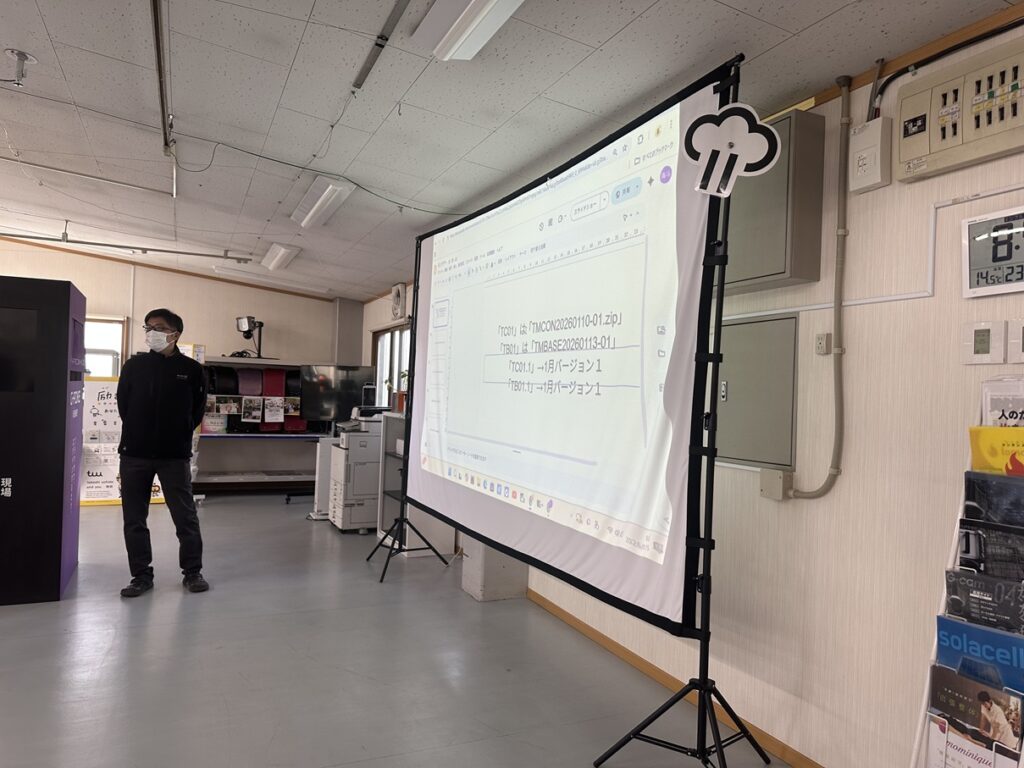2026.02.04
2026年2月4日(水)
謝芳さんの豊富な話題。
田舎の子に、教育の機会を与える制度や、
ガソリン車のNoプレートを新たに交付しない制度。
合理的で理にかなってるものが多い。
政府のコメントに、表と裏があることも、皆分かっている。
寝ころび族の話は日本でも聞いたことがあるが、
訪れた寺院で見た多くの若者たち。
大人は「こういう時ばっかり祈って」と揶揄するが。。
私は、若者の正直な思いを感じる。
皆、求めている「人間主義」という生き方を。
●今日の学び
「幸」の字に「辛」の字が入っているのは、
幸せな時に辛いことや辛い思いをしている人のことを忘れないためである
―こう訴えた詩人がいる。
●ブルガリア科学アカデミー アクシニア・D・ジュロヴァ博士
異なる文化が存在し続けるためには、対話が必要です。
精神性と人間性の保全、そして世界平和に到達する手段ととなるのは対話なのです。
世界平和の希求は、先生の弟子たちへと引き継がれています。
(中略)
先生は土壌を創り出し、”種”をまきました。それは、暴力によるものではなく、結合と相互理解によって実現する、世界平和のための種です。
東哲は、先生の思想を実現するために創立されました。
すなわち、先生の活動の”華”であったと私は考えます。